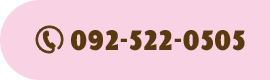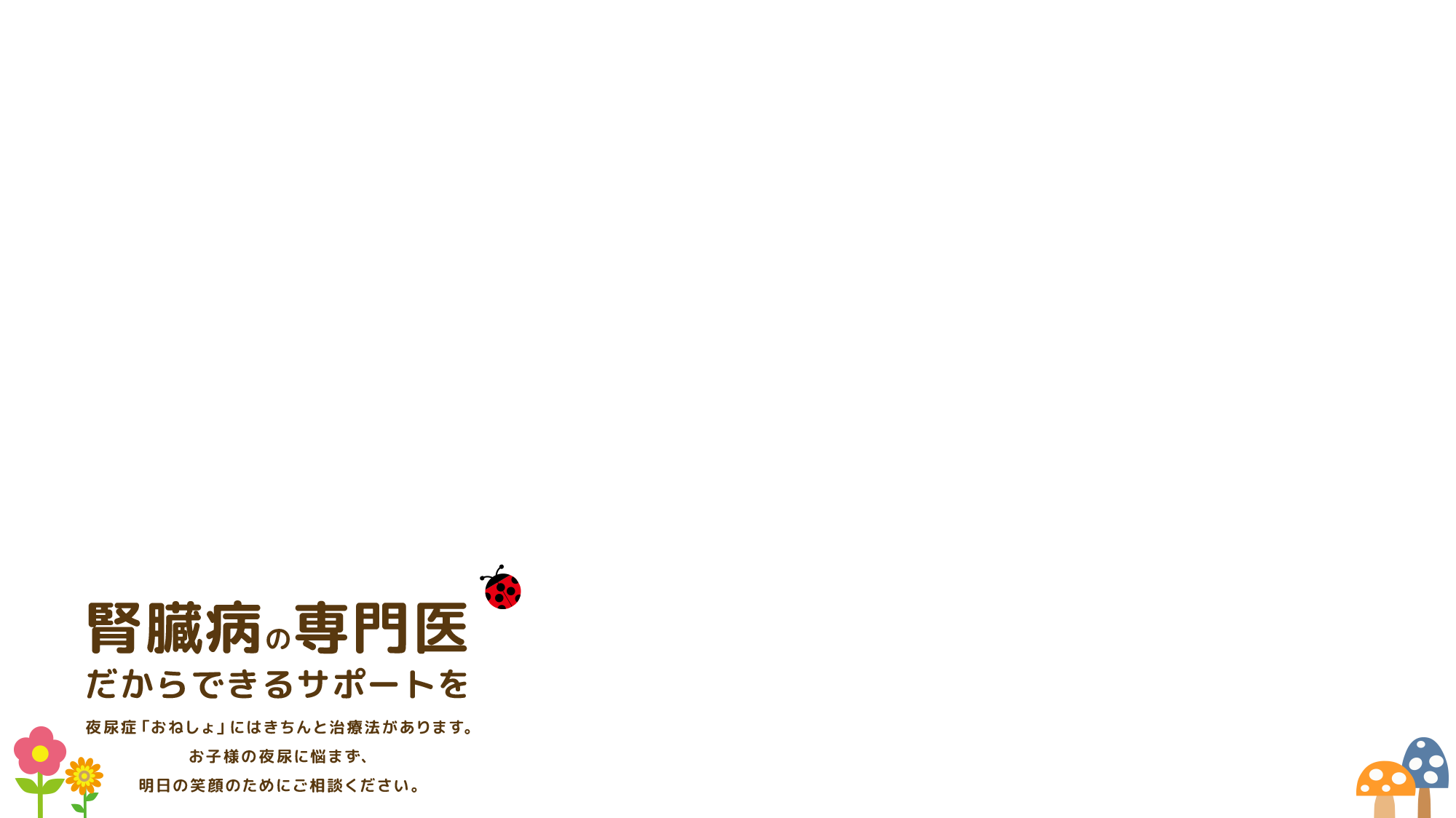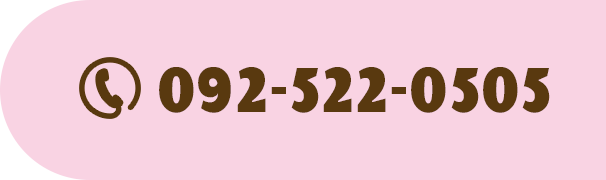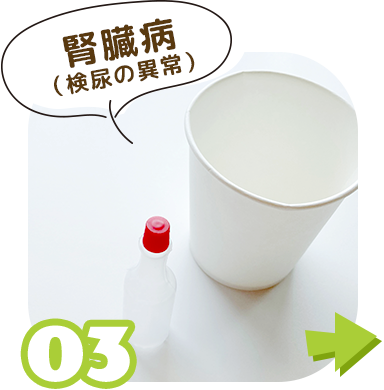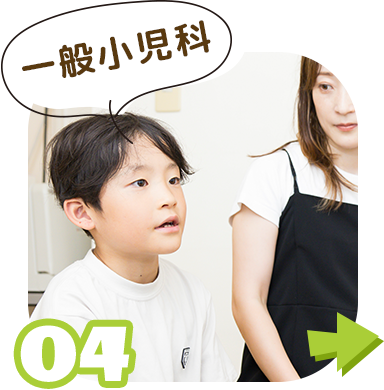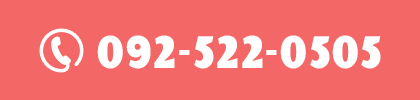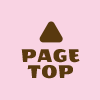お子さまの発育は、いろいろと気掛かりなことも多いことと思います。
反面、毎日接しているから状況に慣れてしまって、
「病院に相談するほどじゃないかな」と、
受診を遠慮する親御さまも多くいらっしゃいます。
当院では、夜尿症(おねしょ)や低身長症、小児の腎臓病に関する専門的な診療を中心に、
お子さまに関する幅広いご相談をお受けしています。
地域のかかりつけ医として、そして子育ての相談場所として、
お悩みだけでなく小さな疑問でも気軽に聞けて
安心できる場所でありたいと思っています。
どんなことでも、気兼ねなくお尋ねください。
クリニック案内CLINIC
〒810-0014
福岡県福岡市中央区平尾2-5-8
西鉄平尾駅ビル3F
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | / |
| 14:00~18:00 | ● | ● | / | ● | ● | / | / |
▲...9:00~14:00
※最終受付は診療時間30分前まで
診療の混雑を避けるため、当院は30分単位の時間帯予約制とさせていただいています。
事前にWEBもしくは電話でのご予約をお願いします。
定期予防接種や乳幼児健診は、専用枠を設けていますので安心してご来院ください。
診療案内MEDICAL
夜尿症と診断されるのは、「5歳以上の子どもで、1ヶ月に1回以上の夜尿が3ヶ月位以上続く場合」です。年齢が進むうちに減っていくものですが、数%は治癒しないまま成人すると言われます。
夜尿症は自尊心の発育や性格形成に大きく関わる症状です。早めに治療を開始し、体と心の健やかな発育を目指しましょう。
低身長とは、それ自体が病気ということではありませんが、何らかの病気が関与しているケースがあり、軽視せず早めに原因を確かめることが大切です。
同じ性別、同じ年齢(月齢)の子供100人を背の順に並ばせた時に、小さい方から2-3番目までの子供を、低身長と定義しています(-2SD)。
つる小児科クリニックでは、学校検尿のご相談も受け付けております。
腎臓病の多くは、病気がかなり進行しないと自覚症状が出現しません。
そのため、保育所や学校で定期的な検尿が施行され、早期発見や早期治療が目指されています。尿の色がおかしい、尿が泡立つ、むくみがある、排尿時に痛い、トイレが近いなどの症状がある場合、まずご相談ください。
一般小児科では、咳や鼻水、発熱、胃腸炎といった内科疾患や、育児相談を受けられます。
幼児や小児の時期は、季節ごとに流行する感染症など、急性の症状が多く見られます。
当院は完全予約制となっていますので、急性の場合でも来院前にWEBもしくは電話にて予約をお願いしております。
乳幼児・小児の各種予防接種に対応しています。年齢とタイミングに合ったワクチン接種で、VPDを防ぎましょう。
感染症との接触を避けるため、専用枠で対応しますのでご安心ください。
なお、予防接種の際は保護者の同伴をお願いしています。
保護者が同伴できない場合は、接種を受けるお子様の健康状態を把握されている親族等が同伴することもできますが、その際は委任状が必要です。(福岡市のホームページからダウンロードできます)

01全国でも珍しい
「夜尿症」「低身長」
「小児腎臓病」を
専門で診るクリニック
当院は、全国でも珍しい「夜尿症」「低身長」「腎臓病」を専門とするクリニックです。いずれも原因をしっかりと見極めなければなりません。生活習慣や栄養の状態、病気の可能性など、あらゆる角度の視点をもって問診や検査を行い、的確な治療を行い改善へ導きます。

02かかりつけの
小児科として
病気・育児相談が
気軽に行える
近年、育児の相談ができる存在が身近にいない人が増えました。
当院では、育児の悩み相談も受け、ご家族皆さまが安心して毎日を過ごすためのサポートをします。
近隣にお住まいのご家族はもちろん、遠方にお住まいの方にもかかりつけ医としてご来院いただいています。

診療は安心の
予約制での診療(専門外来は長めの診療時間)
診察は、感染症対策および混雑を避けるために予約制としております。
専門外来は少しでも詳しく状況を伺うため、一般的な診療より長めの予約枠を確保しています。
急な症状の場合でも、ご来院の前にWEBもしくは電話にて予約を取っていただくようお願いします。

院長、スタッフ
全て女性だけの
チーム
子育てや発育に関する相談は、話しやすい相手と慣れた空間が大切だと考えます。
当院では、院長を含めスタッフ全て女性だけのチームで、ご家族のどなたでも来院しやすく話しやすい雰囲気づくりを心がけています。

「西鉄平尾駅」
直結なので
通いやすい立地
当院は「西鉄平尾駅」の駅ビル内にあり、改札を出てすぐにアクセスすることができます。
駅ビル内にはおむつ替えシートやベビーチェアが備え付けられているトイレやエレベーターも設置され、お子さん連れでも通いやすい環境です。
DEARPARENTS保護者様へ
こんにちは。つる小児科クリニックの院長・檜山麻衣子と申します。
先代である父が2006年に西鉄平尾駅の駅ビルに開院したクリニックを継承しました。
私自身は、腎臓の専門医として、全国にも少ない「夜尿症」「低身長」「小児腎臓病」を専門に診る小児科クリニックとして、診療を行っています。
夜尿症は、厳密に言えば“おねしょ”とは違います。
かつて夜尿症は自然と改善するものとされ、医療機関で診療するものではないと考えられた時代もありました。
しかし現在は「夜尿症は病気であり、治療するべき疾患」と考えられています。
現在、推定78万人の子供たちが夜尿症と言われていますが、残念ながら、いまだに「様子観察」をされている子供たちが大勢いらっしゃいます。
夜尿症が世の中で認知され、お子さまが専門の機関で適切な診療を受けることで、一日も早く夜尿症から解放される朝を迎えてほしいと願っています。
夜尿症、低身長症は、ともすれば見過ごしがちな症状ですが、成長過程のお子さまにとって、適切な時期の対応が必要な症状でもあります。
専門診療を行えるクリニックで正しい知識を得ることは、親御さんの不安の軽減にもつながることと思います。
病気のことだけでなく、お子さんの体とこころの発育に関するお悩みもお聞きしています。
お悩みを相談できる場がないと感じた時も、どうぞお気軽にご来院ください。
小さなお悩みであっても、しっかりと受け止めてお話をお聞きします。